Contents
◎Live Review
Tedeschi Trucks Band
◎Featured Artist & Recommended Albums
Dr. John『Gris-Gris』,『Gumbo』 etc.
◎Coming Soon
Abdullah Ibrahim(a.k.a. Dollar Brand)
◎PB’s Sound Impression
LiveHouse NEPO
構成◎山本 昇
Introduction
エルトン・ジョンの伝記映画『ロケットマン』に感じる懐かしさ

©2018 Paramount Pictures. All rights reserved.
第34回目のA Taste of Musicは、僕にとっては非常に懐かしい東京・吉祥寺に今年オープンした「NEPO」というライヴハウスからお送りします。この新しいお店のユニークな特徴などは後ほどご紹介します。今回は、先日亡くなったドクター・ジョンを追悼特集し、彼の足跡を音楽で振り返ります。どうぞ最後までお付き合いください。
さて、まずは前回に続き映画のお話になりますが、エルトン・ジョンの半生を描いた伝記映画『ロケットマン』を観ました。興味深かったのは子供の頃の話です。本名をレジナルド・ドワイトという少年はあまり幸せな幼児期を過ごすことはできませんでした。戦争から還ったお父さんは感情表現ができない人になってしまい、お母さんは子供のことをあまりかまわないタイプの人でした。彼のことをいちばん世話してくれたのはお婆ちゃんだったんですね。映画では、そういう環境で育ったことで愛情に飢えていたというふうに描かれています。でも、僕からすると、当時のイギリスではそれほど珍しい家庭環境ではないことのように思いました。イギリスの人って---日本人もそうかもしれませんが---そんなに愛情表現をあからさまにはしないんです。あのようなストイックな家庭は、むしろイギリス的だなとさえ感じました。もちろん、それが大多数というわけではありませんが、昔はこういう感じの親もけっこういたなという印象があります。
エルトン・ジョンというと、意外に知られていないのが彼とバーニー・トーピンの関係です。シンガー・ソングライターのエルトンは歌詞を一切書きません。一方、バーニーは歌詞しか書かない。完全な分業制なんですね。先に出来上がるのは歌詞。バーニーが作った歌詞をピアノの譜面立てに乗せて、それを見ながらエルトンが曲を作るんです。昔からいままで、ずっとそうやってきました。
作詞と作曲は基本的には常に別々に作業していたのですが、たまに例外もあって、映画ではあの有名曲が生まれる瞬間が描かれていますが、なかなかいいシーンでした。こうしたエピソードはどれも実際にあったことをわりとそのまま再現しているようですね。そういう意味ではドラッグやゲイ・セックスの場面も出てきますが、それほどどぎついものではなかったように思います。大衆向けの映画としてはそういうシーンは出さないという選択もあり得たのでしょうが、映画の制作総指揮として関わったエルトン本人は自分のありのままを知ってほしいと思っていたそうです。だから、この映画を観ると、荒れていたときの彼はドラッグや飲酒がいかにひどかったかが分かります。そして、AA(アルコホリックス・アノニマス)という組織のグループ・セラピーで、最初はガードを堅くしていた彼も徐々に腹を割って自らのことを話すようになり、そのフラッシュ・バックとリハビリ施設での話が交互に描かれていました。劇中、なぜかときどきミュージカル仕立てになるのです。僕はミュージカルが苦手なので、この演出はいただけませんが、それはさておき、有名な曲はたくさん出てくるし、ライヴのシーンもいろいろあって楽しめる映画だと思います。
その一方で、ビートルズの著作権も管理していたディック・ジェイムズという音楽出版界の大物も登場するのですが、これがまた昔のイギリスの音楽業界によくいたタイプで、いかにもミュージシャンを搾取しそうな男なのです。エルトンは彼が持っていたDJMという音楽出版社と契約するのですが、その後、ジョン・リードというスコットランド人と出会って、エルトンはDJMから抜け、また後にこのジョン・リードとももめることになって……。そのあたりの話はけっこう細かく描かれています。このような音楽業界のあまりきれいじゃない部分は、僕は長くこの業界で仕事をしているから大体のことは分かっていますが、知らない人からするとちょっとショッキングに感じるかもしれませんね。
言うまでもなく、エルトン・ジョンのイギリスでの人気はものすごいものがありました。ど派手なライヴ・パフォーマンスが苦手な僕は、彼の音楽を専らラジオで聴いていました。日本に来る前にレコード店で働いていた頃、シングル「Crocodile Rock」(1972年)やアルバム『Goodbye Yellow Brick Road』(1973年)は本当によく売れました。特に『Goodbye Yellow Brick Road』は低価格の2枚組ということもあって人気があり、カウンターの下にいっぱい用意していたのが飛ぶように売れていました。シングルでは、キキ・ディーとのデュエット「Don't Go Breaking My Heart」も大ヒットしましたが、その録音風景も映画に出てきます。映画『ロケットマン』は、エルトン・ジョンをリアルタイムで聴いていた人には懐かしく感じるでしょう。若い世代にとってはディズニー映画『ライオン・キング』の主題歌「Circle Of Life」でお馴染みなのかもしれませんね。
昨年大ヒットした『ボヘミアン・ラプソディー』はクイーンのことをそんなに知らない人でも楽しく観られる映画でしたが、『ロケットマン』にもそういう面白さはあると思います。もちろん、音楽ファンにもぜひ観てほしい映画ですが、僕のようにミュージカル嫌いの人はちょっと覚悟してください(笑)。

映画『ロケットマン』
8月23日(金)全国ロードショー/配給:東和ピクチャーズ
©2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

『ロケットマン - オリジナル・サウンドトラック』
ユニバーサルミュージック UICR-1146

東京・吉祥寺のライヴハウス「NEPO」のステージに佇むバラカンさん。複数のカメラで捉えた様々なアングルの映像をリアルタイムに映すLEDディスプレイと2台のプロジェクターによりユニークな視覚効果を演出している
Live Review
メンバーの死を乗り越え、前進する大所帯バンド
Tedeschi Trucks Band at Tokyo Dome City Hall
![6月14日、東京ドームシティホールでのステージから。[撮影:土居政則]](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol34/v34_05.jpg)
6月14日、東京ドームシティホールでのステージから。[撮影:土居政則]
テデスキ・トラックス・バンドが3年ぶりに日本にやってきました。6月に大阪・名古屋・東京で行われた日本ツアー。僕が観たのは14日の東京ドームシティホールでの公演です。
テデスキ・トラックス・バンドはメンバーに変化がありました。かねてからデレクの右腕的な存在だったキーボードとフルート奏者のコーフィ・バーブリッジが、彼らのニュー・アルバム『Signs』が出た今年の2月15日に亡くなってしまったんです。2年くらい前に心臓発作で入院して手術を行い、しばらくバンドを休んで元気になっていましたが、去年の暮れ頃からまた体調を崩し、結局57歳でこの世を去りました。メンバー全員にとって大変なショックであったことは言うまでもありませんが、特にデレク・トラックスは20年来の付き合いですから、相当な落胆だったはずです。そんな彼に代わるキーボード奏者としてツアーに参加したのがゲイブ・ディクスンでした。また、ベイシストのディム・ルフェーヴも脱退して、代わりにブランドン・ブーンという若手が加入しています。
テデスキ・トラックス・バンドはとにかく大所帯のバンドで、前回の来日公演とメンバーの数は同じだったと思います。バック・ヴォーカルは3人、男性2人と女性1人ですが、みんなすごく上手くて、それぞれがフィーチャード・ヴォーカリストになれるくらいの才能の持ち主です。ホーン・セクションも3人で、サックスとトランペットが男性、トロンボーンが女性なんです。もちろん今回もドラムズは2人、これにキーボードとベイス、メイン・ヴォーカルとギターのスーザン・テデスキ、そしてデレク・トラックスの計12人編成です。デレクはこの来日中に40歳になりました。スーザンは彼より9つ年上です。他のメンバーは大体30代だと思いますが、いずれにせよ、そういう世代のバンドなのにやっているのは僕の世代に響く音楽です。ちょっと珍しいバンドですよね。
デレクはオールマン・ブラザーズ・バンドの環境で育ったこともあり、オールマンを好きだった世代がそのままデレクのバンドも聴いています。とにかく演奏は上手い。デレクからして、世界でも彼以上に上手い人はいないと言われるほどのすごい才能です。ほかのメンバーももちろん上手くて、バンド全員がとても真剣に臨んでいるという雰囲気がステージからひしひしと伝わってきます。そんなコンサートは彼らの音楽をそれほど知らなくても楽しめます。初めて見に行ったという僕のラジオ番組のリスナーも、みんな感激していました。演奏に対する真剣な気持ちがそう感じさせるんだと思います。会場に集った人の年齢層も、今回は若い人の姿も見え、少しずつ多様になっていきているようです。東京公演の会場もちょうどよかったと思います。下がアリーナで、その周りにスタンド席があって、ステージとの距離もそんなに遠くないから観やすいし、音も悪くなかったと思います。僕はアリーナで観ましたが、とてもいい雰囲気のコンサートでした。
セット・リストは、オリジナルが半分ちょい、あとはいろんな人たちのカヴァーで、ブルーズやソウルなどいろんなタイプの曲をやります。彼らのライヴを観ると気付くと思うのですが、デレクは客席のほうをあまり見ずに、わりといつも横向きで弾いています。確かに、自分もリーダーのはずなのに、“テデスキ・トラックス・バンド”とスーザン・テデスキのほうを先にもってきていることからも分かるように、一貫して奥さんのスーザンのことを立て、彼女をバンドの中心に据えています。このバンドができてからもう10年近く経ちましたが、彼はそのサポートに徹しているように思います。その前のデレク・トラックス・バンドのときは、彼が中心だったしソロももっと多かったのですが、あの頃からステージ・マナーは地味でした。ギターを弾きながら海老ぞったりは一切しない(笑)。まぁ、少しシャイなところがある人だけど、バンドのリーダーとしてほかのメンバーに目配せするために横を向いたり後ろを向いたりしていますが、決してお客さんに対して冷たいというわけではないんですね。
その中心人物であるスーザン・テデスキですが、僕がこれまで観てきた中で、彼女は今回のライヴがいちばん良かったと思いました。パワー感のあるシャウト型のブルーズ・ヴォーカリストなので、ときに一本調子と捉えられることもあります。今回は、力の入れ具合を加減するところがあったりして、3年前に比べてヴォーカリストとして幅が出てきたような気がしました。そして、彼女のギターも一段と良かったんです。ライヴでは必ず1曲、彼女が長いギター・ソロを弾きます。僕が観た14日はボビー・ブランドの「I Pity The Fool」でした。もう、炸裂するようなギター・ソロを披露して客席を沸かせていました。デレクと違って彼女のギターは黒っぽいんです。昔の黒人のブルーズ・ギタリストが弾くようなギターなんです。そんなテイストをあそこまで出せる白人のギタリストは男性でも女性でも、ほとんどいないと思いますね。デレクはデレクで独特のスタイルを築いていて素晴らしく、白人も黒人も関係ないユニークなサウンドを持っています。
新しく入ったキーボードのゲイブ・ディクスンも、まだ手探りではあるのでしょうけれど、演奏は上手でした。亡くなったコーフィーへのトリビュートとして、ダニエル・ラノワがプロデュースしたウィリー・ネルスンのアルバム『Teatro』に入っている「Somebody Pick Up My Pieces」をスーザンが歌い、ゲイブがハモっていましたが、これも良かったです。当然、コーフィーとは持っている雰囲気は違いますけど、彼なら今後もこのバンドでやっていけそうだなと思わせてくれました。彼がキーボードのソロを弾くとき、デレクが近付いて行って応援するような素振りを見せていたのも微笑ましいですね。やはりデレクはバンド・リーダーとしての役目を真面目に考えているんだなと思いました。そのデレクは得意のスライド・ギターもけっこう弾いていて嬉しかったですね。そのほか、デレク・トラックス・バンドのリード・ヴォーカリストだったマイク・マティスンがバック・ヴォーカルを務めていて、彼がデレク・トラックス・バンドの頃のレパートリーを歌ったりしたのも良かったと思います。
何しろコーフィーはこのバンドのもう一つの要でもあったから、どうなるのかと心配ではあったのですが、このコンサートを観て僕は安心することができました。ただ、コーフィーのフルートがないのはちょっと残念ですけどね。メンバーでサックス奏者のケビー・ウイリアムズはフルートもできるらしいのですが、コーフィーのフルートがあまりにも良かったから、あえてこれまでは吹かなかったそうです。でも、デレクとしてはケビーにもそのうちにフルートも吹いてもらおうかなと、そんなことも言っていました。
デレク・トラックスには、来日前に僕が電話でインタヴューをしていて、それが電子音楽雑誌『ERIS』の第27号に載っています。興味のある方はどうぞご覧ください。

『Signs』ユニバーサルミュージック UCCO-1203

撮影:土居政則

撮影:土居政則

撮影:土居政則

撮影:土居政則

撮影:土居政則

撮影:土居政則
Featured Artist & Recommended Albums
追悼特集 Dr. John
「ニュー・オーリンズの音楽文化を世界に広めた功績は計り知れません」

photo by Bruce Weber
ドクター・ジョンが6月6日に、77歳で亡くなりました。マルコム(通称“マック”)・レベナックという本名を持つ彼が生まれたのは1941年、ニュー・オーリンズです。お父さんは街で家電屋さんを営んでいたんですが、それがつぶれてしまうとレコード店を始め、傍らでラジオやテレビ、さらにはクラブのPAシステムといった電気関係の修理を半ばボランティアで引き受けていたそうです。クラブのPAの修理に出向くとき、お父さんはよくマックのお姉さんを連れて行ったらしいのですが、まだ小学生のマックはそのたびに「僕も連れて行って」と頼んでいたそうです。クラブではいろんな音楽をやっていたので、マックもそれを聴くのが楽しみだったそうです。あるいは、お父さんのお使いで、近くのバーにビールを買いに行くときも、お駄賃でよくジューク・ボックスを聴いていたそうです。そこで聴けるのは主にブラック・ミュージックですね。
そんな彼が音楽を始めたとき、楽器はギターでした。ニュー・オーリンズでも有名なギタリストに教わり、12~13歳のときにはすでにセミ・プロのような腕前だったと言われています。ライヴで演奏するのはお酒が出るところだから、最初は年齢を偽っていたそうですね。15~16歳の頃には彼がバンド・リーダーとなってレコーディング・セッションも始めたり、アレンジャーやプロデューサーのようなこともやったりしていました。もちろん、作曲もし始めます。自らのバンドでニュー・オーリンズのクラブに出ていたようですから、早熟と言えば早熟な人だったと言えるでしょう。ただ、ニュー・オーリンズのクラブというと、麻薬や売春と隣り合わせ。ジャズ発祥の地と言われるストーリーヴィルという街は、いわゆる赤線地帯です。当時のニュー・オーリンズはそういう猥雑なところがあって、またそれを取り締まることがあまりない時代でもありました。そういう時代の音楽は元気なんですね。お客さんもたくさん来るし、みんなよくお酒を呑む。つまり、ライヴ・シーンが活発になります。でも、1960年代に入ると、ジム・ギャリスンという有名な地方検事が突如、風俗の取り締まりを強化したんです。それでニュー・オーリンズでは閉鎖を余儀なくされるクラブが続出して、気が付いたらミュージシャンが演奏する場所がほとんどなくなってしまいました。
そんなあるとき、彼のバンドでヴォーカリストをしばらく務めていたロニー・バロンという仲のいいキーボード奏者が、何かのトラブルで悪いヤツに襲われそうになったとき、マックが彼を守ろうとして身を挺したら左手を撃たれてしまったんですね。それでギターを弾くことができなくなり、代わりにピアノを演奏するようになります。以前もピアノは弾いていたのですが、ニュー・オーリンズには素晴らしいピアニストが山ほどいるので、自分のピアノは通用しないと考えてギタリストを選んだそうなんですね。でも、結局そんなことがあってピアノを本格的に弾き始め、ニュー・オーリンズを代表するピアニストとなりました。
ニュー・オーリンズとヴードゥー教
ニュー・オーリンズにはいまもミュージシャンがたくさん住んでいますが、60年代の前半には多くの人が主にL.A.に移住していきました。当時はまだマック・レベナックと名乗っていた彼も、アルコールやドラッグに早くから手を出していて、何度かしょっ引かれ、豚箱で過ごしたこともありました。何度目かの逮捕のときは刑務所に行くか、リハビリに行くかということになり、テクサスのリハビリ施設にしばらく入所しています。そこを出るときには、仲間のミュージシャンもニュー・オーリンズにはほとんどおらず、彼も仕方なくL.A.に向かいました。L.A.では彼の先輩のミュージシャン、ハロルド・バティストがプロデューサーやアレンジャーとして活動していました。ハロルドが関わっていたプロジェクトの一つにサニー&シェールという夫婦によるポップのデュオがあり、いいミュージシャンをバックに起用していました。サニー・ボーノも、フィル・スペクターのもとでソングライターやアレンジャーとして活動していました。そのフィル・スペクターがいつも使っていたゴールド・スターというスタジオを、ハロルドは友達のよしみで夜の間、マックに貸し与えたんですね。
ところで、マックが生まれたニュー・オーリンズではヴードゥー教が信仰されていました。基本的にはアフリカの宗教ですが、キューバではサンテリア、ハイチではヴォダンと呼ばれて信仰する人も多く、ニュー・オーリンズにはハイチの人も多く住んでいます。マックも、ヴードゥー教の人と仲が良かったりして、本もよく読んでいたそうです。余談ですが、日本で小泉八雲として知られるラフカディオ・ハーンは、日本に来る前にニュー・オーリンズで新聞記者をしていて、ここの風土や文化について、新聞や本に書いていました。マックもそれを読んで、ヴードゥーの司祭である“ドクター・ジョン”が、“ポーリーン・レベナック”という女性と関係があることを知ります。レベナック姓を持つ彼は、もしかしたら遠い親戚かもと思い、またそのドクター・ジョンという司祭も気になってくる。興味の対象がいつしかヴードゥーの音楽を含めた文化全体におよんだ彼は、そういうレコードを作ろうと思い始めます。
ハロルドが手配してくれたスタジオで、マックが作ろうとしたのはそんなアルバムで、ニュー・オーリンズからL.A.に移住したたくさんのミュージシャンも参加して出来上がったのがドクター・ジョンの名義で発売された『Gris-Gris』(グリ・グリ)というかなり変わったレコードでした。このアルバムが出た1968年の時点ではドクター・ジョンのことは誰も知りません。このジャケットに写っているキャラクターはアルバムのために作ったものですが、ほとんどモンスターですよね。当時、高校生だった僕はこのアルバムを買いましたが、なぜ買ったのかがいまだに思い出せない(笑)。特にニュー・オーリンズということを前面に出しているわけでもないし、裏ジャケに載っている本人が書いた文章も、何を言っているのかよく分からない。とにかく不思議なレコードなんだけど、これが実に素晴らしい。ヘンなレコードだけど名盤なんですよ。
ではこの『Gris-Gris』から、1曲目の「Gris-Gris Gumbo Ya Ya」を聴いてみましょう。ベイスがまるでルーツ・レゲエみたいですごいですね。時代はサイケとは言え、メチャクチャ怪しい(笑)。次の「Danse Kalinda Ba Doom」も不思議な曲で、当時はこんな音楽を聴いたことがありませんでした。でも、このサウンドはなぜか一発目からハマるんですよ。メロディアスだしリズミックだし、反復が多いから聴いているうちにどんどん引き込まれていくんです。この曲はおそらくハイチの雰囲気が出ているんだろうけれど、もちろん当時はそんなこと何も知らないから、摩訶不思議なレコードとしか言えませんでした。3曲目の「Mama Roux」はわりと分かりやすい曲で、R&Bやソウルを聴いている人間には親しみやすいですね。そして、この女性コーラス。よく聴くとハーモニーが微妙にズレていますが、気持ち悪くないんですね。このアフリカというか、カリブ的な音感を、少なくとも僕はこのレコードで初めて聴きました。高校生だから、あまり理屈で音楽を捉えているわけではないので、こういう感覚的な音感も自然に身に付く。ニュー・オーリンズの文化もまだ何も知りませんでしたが、結果的にこのアルバムはそこに繋がるような感覚を届けてくれました。最後の「I Walk On Guilded Splinters」は、ドクター・ジョンが生涯を通じてライヴで演奏し続けた曲です。はっきりとは分からないけど、歌詞はどうやら黒魔術の世界のことを歌っているようです。音楽の雰囲気も不気味ですが、なぜだかこれもハマってしまうんですよ(笑)。契約したアトランティック・レコード社長のアーメット・アーティガンも、このアルバムを聴いて「こんなの、どうやって売れというんだ!」って文句を言ったそうです。ただ、スタジオ代はほとんどかかっておらず、レコード会社として大きな投資をしたわけではないから、「まぁいいか」ということになったらしいです。発売当時、大して売れたわけではありませんが、一部ではちょっと話題になった作品です。
ドクター・ジョンはこの後に、『Babylon』(1969年)と『Remedies』(1970年)という、どちらかというと1枚目の『Gris-Gris』と同じような雰囲気のアルバムを出しますが、この初期の3作の中では断トツに『Gris-Gris』が面白いです。これらはアメリカではほとんど注目されませんでしたが、ヨーロッパでは興味をもって取り上げる音楽ライターや雑誌の編集者がいたり、あるいはジョン・ピールあたりがラジオでかけたりしていました。

NEPOのサウンド・システムで試聴中のバラカンさん。「ほとんどスタジオで聴いているような感じですね。ヴォリュームを大きくしなくても十分いい音だと思いました」
そんな折り、ドクター・ジョンはヨーロッパ・ツアーを行うんですね。そのツアーのついでに、イギリスでアルバムも録音しました。タイトルは『The Sun, Moon & Herbs』。つまり、太陽・月・そして薬草ですね。これもヴードゥーの発想に基づく企画だったんですが、エリック・クラプトンやミック・ジャガーなどいろんなミュージシャンがゲスト参加しています。ただ、このときのドクター・ジョンのマネジャーがまたヤクザっぽいヤツで、アトランティックとの契約があるにもかかわらず、ここで作ったマスター・テープをほかのレコード会社に売り込んだんです。それを知ったドクター・ジョンは怒って、マスター・テープを取り戻します。しかし、そのマスター・テープはマネジャーに勝手にいじられていて、あるはずの音が消されていたり、ないはずの音がダビングされていたりして、ドクター・ジョンが意図したアルバムとは全然違うものになっていました。そこでもう一度、思い通りのアルバムに戻すために、アトランティックがマイアミに持っているクライデリアというスタジオでその作業を行います。
その頃、アトランティック・レコードの副社長だったジェリー・ウェクスラーは半分マイアミに住んでいて、スタジオにやってきてはドクター・ジョンといろんな話をしたそうです。ジェリー・ウェクスラーと言えば、かつて社長のアーメット・アーティガンと二人でニュー・オーリンズに乗り込んでプロフェサー・ロングヘアを録音したり、昔のリズム&ブルーズのことも熟知している人です。そういう昔のニュー・オーリンズの音楽について話し合っているうちに生まれたのが1972年に発売された『Dr. John's Gumbo』です。それまではずっとヴードゥーの文化を音楽で表現するようなことやっていたんですが、さすがにそれに少し飽きてきて、違うことをやりたいと。おそらく、このときのドクター・ジョンには自分が生まれ育ったニュー・オーリンズの古いR&Bと正面から向き合ってレコードを作るという発想はなかったと思います。でも、ジェリー・ウェクスラーとの話し合いで彼に発破をかけられこういうレコードが見事に出来上がります。
このアルバムには、ドクター・ジョンがジェリー・ウェクスラーに語った話が曲の解説として付いていました。当時、主に1950~60年代の前半くらいのニュー・オーリンズのR&Bについて詳しく知っている人はほとんどいませんでした。プロフェサー・ロングヘアもアール・キングも、ヒューイ・スミスのことも知られていません。そもそも50年代あたりの音楽を、60年代に聴こうという習慣はあまりありませんでした。古いロックン・ロールなどをオールディーズとして楽しむようになったのは、結局70年代から始まった文化なんです。ちょうど僕が学生の頃に50'sのロックン・ロールのベスト盤などがたくさん出るようになりました。このドクター・ジョンの『Gumbo』も、そんな文化の中で生まれた作品と言えるでしょう。アルバムには、それまでに聴いたことのない、面白い音楽が詰まっていました。
まず、1曲目の「Iko Iko」で、「あの『Gris-Gris』のドクター・ジョンがこんなことしているの?」と驚くわけです(笑)。さらに、何を歌っているのかこの歌詞がよく分からない。「Iko Iko」は英語ではなく、クレオールの言葉というか、いわゆるマルディ・グラ・インディアンの世界なんだけど、当時はそんなことも知りません。でも、曲はご機嫌です。もちろん、このセカンド・ラインと言われるビートのことも当時は知らなくて、僕はボー・ディドリーの音楽のビートに近いなと思っていました。最初にこの曲を聴いたのはラジオの番組で、DJのチャーリー・ギレットがこのアルバムのバック・グラウンドを説明していたのですが、それがすごく面白かったんです。そこですぐにレコードを買いに走って、例の曲解説を読めばいっそうこの世界に興味が湧いてきました。続いては、どれも名曲ばかりですが、9曲目の「Tipitina」を聴きましょう。当時、僕のようなブルーズが好きな人は、いろんなスタイルのブルーズ・ピアノは聴いていましたが、こんなピアノはまず聴いたことがありませんでした。本当に独特で、転がり込むような感じでもあり、のんびりしているようでもあり。いろんなリズムがぶつかり合っているというか、このシンコペイションの感覚がとても不思議でした。作曲のクレジットはロイ・バードとなっているんだけど、解説を読むとそれはプロフェサー・ロングヘアのことだと書いてある。「プロフェサー・ロングヘアって誰?」という感じなんですけど(笑)、この「Tipitina」という曲があまりにも面白いから、その名前にも興味を持ちました。するとその直後に、アトランティック・レコードから1940~50年代に録音された彼のアルバムが初めて『New Orleans Piano』というタイトルのLPで出たんです。このように、『Gumbo』がきっかけとなってプロフェサー・ロングヘアも、にわかに注目されるようになりました。その頃、彼はすでに50代半ばだったはずです。ちなみに、ニュー・オーリンズにはマルディ・グラというお祭りがあり、「Mardi Gras in New Orleans」という彼の曲が街中で流れるから、ニュー・オーリンズでは知られた存在でした。でも、当時はそれほど仕事もないので、得意の博打で稼いでいたと言われていますが、もちろん豊かではなかったようです。ようやく70年代になると、ドクター・ジョンの『Gumbo』のおかげもあってニュー・オーリンズの音楽が注目されるようになり、プロフェサー・ロングヘアもテレビに出たりして仕事も増え、新しいアルバムも作っています。1980年の1月に61歳でなくなりましたが、晩年はその存在感を世界に示すことができたと思います。
とにもかくにも、ドクター・ジョンの『Gumbo』は、ニュー・オーリンズという街の過去の音楽文化がこんなにも面白いんだということを広く世界に紹介したレコードでした。音楽そのものの良さだけでなく、ニュー・オーリンズという街が、独自の文化を持っていることを最初にみんなに知らせてくれたレコードとして、このアルバムの意義は大きいんです。取り上げているのはレイ・チャールズやヒューイ・スミス、アール・キングあたりをメインとした曲のカヴァーで、ドクター・ジョンのオリジナルは「Somebody Changed The Lock」のみです。ドクター・ジョンは基本的にはピアノを弾いていますが、「Let The Good Times Roll」ではギターも演奏しています。録音はL.A.ですね。僕にとっても大愛聴盤です。

『Gris-Gris』ワーナーミュージック WPCR-16378

『Gumbo』ワーナーミュージック WPCR-18021
アラン・トゥーサントやミーターズも参加した作品もお勧め
その『Gumbo』の次に出たのが1973年の『In The Right Place』です。このアルバムの1曲目「Right Place Wrong Time」は全米トップ10入りを果たし、彼の最大のヒットとなりました。いま聴いても格好いいですねぇ。参加ミュージシャンを見てみると、『Gumbo』のほうはロニー・バロンやハロルド・バティストらニュー・オーリンズでは知られてはいるものの、当時はそれほど有名ではない人がほとんどでしたが、『In The Right Place』はミーターズやデイヴィッド・スピノザといった名前が並んでいます。ただ、ミーターズも、ちょうどこの頃にみんなが注目し出したというタイミングです。プロデューサーはアラン・トゥーサントで、編曲とピアノなどの演奏も行っています。いま考えれば、ニュー・オーリンズのオール・スター・バンドで臨んだようなアルバムですが、当時はむしろこのアルバムのヒットによって彼らの名前が知られた面もあったと思います。それにしても、この『In The Right Place』も素晴らしいアルバムです。『Gumbo』はほとんどがカヴァーでしたが、このアルバムは逆にドクター・ジョンのオリジナルがほとんどです。ではその中からもう1曲「Such A Night」を聴いてみます。このトロンボーン! 管楽器の使い方が実に上手い。アラン・トゥーサントの才能ってこういうところにも顕れるんですよ。たまらないですね。この曲はザ・バンドの『The Last Waltz』でドクター・ジョンが歌っていましたが、当時、このライヴを映画で観た人にとっては、こういうちょっと変わった歌を歌うおじさんというふうに映ったのではないでしょうか。先日放送したラジオ番組の追悼特集でもこの曲の人気は断トツで、しかも「『The Last Waltz』のヴァージョンで」というリクエストも多かったです。映像の力というのもすごいものですね。
もう一枚、ドクター・ジョンのアルバムを。1974年に出た『Desitively Bonnaroo』は、成功した『In The Right Place』とほとんど同じチームで作ったアルバムで、プロデューサーはアラン・トゥーサントが務め、ミーターズらが参加しています。この『Desitively Bonnaroo』はシングル・ヒットがなかったから、あまり語られることがないのですが、出来映えは『In The Right Place』と比べても全く遜色ないです。
ところで、ドクター・ジョンは変な言葉を作るのが好きな人で、5曲目の「Mos' Scocious」というのも彼の造語で特に意味はありません。彼は会話の中でさえ、誰も聞いたことのないような言葉をポンポン入れてくるから、それがまた可笑しくて(笑)。アルバム・タイトルの『Desitively Bonnaroo』もそうですね。“Desitively”はおそらくpositively(積極的に)とdefinitely(絶対に)を交ぜた言葉でしょう。“Bonnaroo”はフランス語を基にした言葉で“素晴らしい”といったニュアンスかな。アメリカの音楽祭にボナルー・フェスティヴァルがありますが、この名称は『Desitively Bonnaroo』から取ったそうですから、意外に影響力のあるアルバムなんてすね。演奏もいいし、曲もいい。何年か前にジョン・クリアリーから聞いたところによると、ボナルー・フェスティヴァルでこのアルバムを再現したことがあるそうなのですが、上手くいかなかったそうです。それはたぶん、リハーサルをしっかりやらなかったからでしょう。ニュー・オーリンズのミュージシャンはジャム・セッションが好きだから、リハーサルもなしにその日の気分でやってしまうことが多いんです。でも、先ほどもお話ししたように、アラン・トゥーサントの編曲はすごく緻密にできているので、その分ちゃんとリハーサルをやらないとグチャグチャになってしまうんですね。
その後、ドクター・ジョンはトミー・リプーマがやっていたホライズン(Horizon)というA&Mの子会社のようなレーベルで『City Lights』(1978年)と『Tango Palace』(1979年)という2枚のアルバムを出していますが、どちらもなかなかいい作品です。ニュー・オーリンズのミュージシャンはいないんですが、ウィル・リーやスティーヴ・ガッド、リチャード・ティーなどニュー・ヨークの一流スタジオ・ミュージシャンが参加していて、いい曲もいっぱいあります。特に『City Lights』は素晴らしいアルバムですね。その後には、『Dr. John Plays Mac Rebennack』(1981年)と『The Brightest Smile in Town』(1983年)というピアノ・ソロを2枚、クリーン・カッツ(Clean Cuts)というレーベルに残しています。弾き語りで、昔のブルーズやスタンダードを歌っています。オリジナルも少しあるけど、ほとんどがカヴァー曲となっています。ドラッグをなかなかやめられなかったドクター・ジョンは、ヘロインで調子を悪くして、しばらくお休みということになるんですね。そういう時期に、クリーン・カッツから声をかけられたわけですが、本当だったらソロ・ピアノなんか怖くてできなかったはずで、自伝でもこのときは緊張したと語っています。でも、すごくいいアルバムなんですよ。
そして、トミー・リプーマともう一度組んで作ったのが1989年の『In A Sentimental Mood』で、全曲がスタンダードのカヴァーです。リキ・リー・ジョーンズとのデュエット「Makin' Whoopee!」がグラミーを受賞するなど、このアルバムはかなり話題になりました。
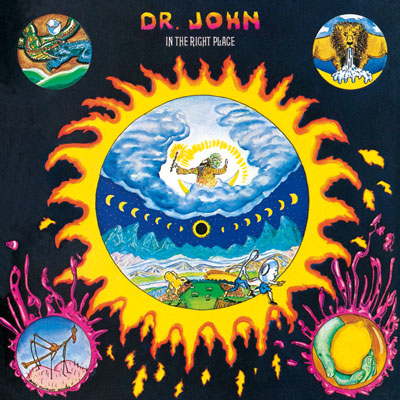
『In The Right Place』ワーナーミュージック WPCR-14835

『Desitively Bonnaroo』
ジャズ作品にも独自の足跡を残したドクター・ジョン
そして1992年、アルバム『Goin' Back To New Orleans』でドクター・ジョンは故郷であるニュー・オーリンズで初めて録音を行います。昔からニュー・オーリンズでやっているミュージシャンが大勢ゲストで参加した、すごく豪華なレコードです。いちばん最後に収録されたアルバム・タイトル曲を聴くと、基本的にはR&Bでファンキーな感じですけど、曲そのものはまだR&Bが生まれて間もない1950年代初頭にジョー・リギンズが作ったものです。途中でクラリネットやトランペットが出てきたり、かつてのニュー・オーリンズ・ジャズの雰囲気がちょこっと顔を見せています。ニュー・オーリンズの音楽はこのように長い歴史を持っていて、ジャズやブルーズ、R&Bなどいろんなものがあるんですが、それらが全部このアルバムに入っています。「Basin Street Blues」は初期のニュー・オーリンズ・ジャズの有名曲だし、「Careless Love」も1920年代の古い曲です。そうかと思えば、1950〜60年代の曲もやっている。そんな歴史に残る名曲をたくさん取り上げているこのアルバムは音もすごくいいんです。プロデューサーのスチュワート・レヴィーンはクルセイダーズを手がけたことで知られた人で、エンジニアのアル・シュミットはアナログの世界で最も有名な人ですね。演奏も素晴らしい、曲もいい、音もいい。数あるドクター・ジョン作品の中でも、かなり上位にランクされるべきアルバムだと思います。スタジオはアルトラソニックですね。ちなみにジャケットは、ドクター・ジョンがマルディ・グラ・インディアンの格好をしている写真です。
お勧めアルバム最後の一枚は『Duke Elegant』。これがまたすごく面白いアルバムなんです。ドクター・ジョンがデューク・エリントンの曲ばかりを特集した作品で、1999年にブルーノートから発売されました。13曲中、ほとんどがデューク・エリントンの有名曲ですが、誰も知らない曲が3曲ほど入っていたり、相当渋い選曲もしています。今日は「スイングしなけりゃ意味ないね」の邦題でお馴染みの「It Don't Mean A Thing」をかけてみます。このハモンド・オルガンを弾いているのはもちろんドクター・ジョンですが、こんなファンキーなデューク・エリントン、誰も聴いたことないでしょう?(笑)。アルバムのプロデュースは本人で、この頃からは彼のツアー・バンドと録音するようになっています。ニュー・ヨークに住んでいる彼の、ある意味では普段着の世界がレコードに刻まれるようになった時代です。
デューク・エリントンとドクター・ジョンは対極にある存在のように感じますけれど、本人はエリントンをもちろんリスペクトしているし、このアルバムを聴けば曲をよく知っているのが分かります。でも、ドクター・ジョンはどんな素材を使っても必ず自分のスタイルにできるんです。それがまた格好いいところで、彼がやると、すぐさまヒップなものになってしまう。僕はこのアルバムもかなり好きですね。いま、Webで「どうしても手放せない21世紀の愛聴盤」という連載を持っているんですが、そこに真っ先に上げたのがこのアルバムです。でも発売したのは1999年の12月だから、ギリギリ20世紀なんだけど、まぁいいでしょう(笑)。
いまはニュー・オーリンズの音楽は広く認知されています。でも、先ほどもお話ししたように、『Gumbo』というアルバムが出ていなければ、ニュー・オーリンズの過去の遺産はみんな知らないままになっていた可能性もあります。そして、昔のものや新しいもの、オリジナルの曲も含めて素材はいろいろあっても、ドクター・ジョンはそのすべてを自分のサウンドにできるミュージシャンだったと、あらためてそう思います。若い人にお勧めなのは……やっぱり『Gris-Gris』かな(笑)。僕も17歳で聴いたレコードです。まったく得体の知れない不思議な音楽だったけど、それを素直に聴いてハマってしまうという、すごく引力の強いアルバムだと思います。そういう体験を、いまの若者がするのも面白いかもしれません。いまから50年以上前の作品ではあるけれど、あの不思議さはいまも変わらない。ぜひ聴いてみてください。

『Goin' Back To New Orleans』
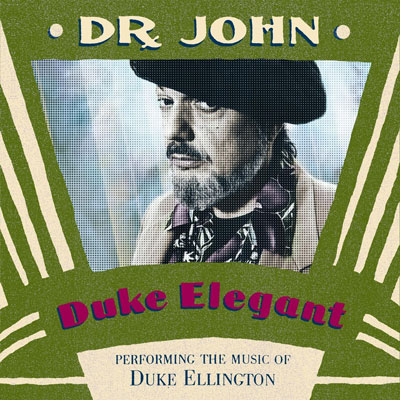
『Duke Elegant』
Coming Soon
南アの伝説的ジャズ・ミュージシャンによるソロ・ピアノ・コンサート in 京都
Abdullah Ibrahim(a.k.a. Dollar Brand)
「LUSH LIFE Presents アブドゥーラ・イブラヒム ソロピアノコンサート2019 」
京都・上賀茂神社 庁屋
2019年9月28日(土) 開場 17:00 / 開演 18:00
2019年9月29日(日) 開場 16:00 / 開演 17:00
*コンサートの詳細はこちらへ。電話での問い合わせはTel.090-1968-9908まで。

かつてドラー・ブランドという名前で知られた南アフリカの伝説のピアニスト、アブドゥーラ・イブラヒムが京都でソロ・ピアノの公演を行います。この6月に出た5年ぶりの新作『The Balance』は久々にエカヤ(Ekaya)という自らのグループでのレコーディングでしたが、このところはソロ・ピアノのアルバムがしばらく続いていて、それも瞑想的な作品が多かったんですね。新しいアルバムは、静かなのもあるけれど、元気のある曲もあり、今年の10月で85歳になる年齢を考えるとすごいなと思います。南アフリカの出身で、アパルトヘイト時代はほとんど亡命生活を強いられるなど、大変な時期もあったはずです。
デューク・エリントンに認められたアブドゥーラ・イブラヒムが尊敬するのは、そのエリントンとセロニアス・マンク。新作でもマンクの「Skippy」を取り上げています。ドラー・ブランドの名義だった頃に初期のECMから出した『African Piano』が録音されたのは、ちょうど50年前の1969年で、日本のジャズ・ファンにはこのアルバムが好きな人も多いことでしょう。今回の来日は度々訪れている京都の上賀茂神社の庁屋 (ちょうのや)という重要文化財の中でのソロ・ビアノ・コンサートということですが、興味のある方はぜひ足を運んでみてください。

『The Balance』

PB’s Sound Impression
新感覚なライヴハウス「NEPO」のPAシステムを聴く
「ヴォリュームを上げなくてもいい音で聴けるスタジオ・モニターのようですね」
東京・吉祥寺駅からゆっくり歩いて約15分。井の頭公園のすぐそばに今年オープンした「NEPO」は、小規模ながら従来のライヴハウスのイメージを覆すようなアイデアに満ちた新しい音楽空間として注目されています。今回、バラカンさんが持ち込んだCDを素晴らしい音で聴かせてくれたそのサウンド・システムは、爆音PAとは対局にあるようなクリアな鳴りが自慢です。なぜ、そんな音を目指したのか。お店を造り、運営するNEPOの中心人物である(株)キルク代表取締役社長の森大地さん、同社社外取締役の白水悠さんにバラカンさんがお話を伺いました。(編)

目の前の井の頭公園をバックに、NEPOの森大地さん(左)、白水悠さんと
このキャパだからこそこだわった音と映像
PB 面白いスペースですね。このお店はいつから?
森 今年の3月から始めました。
PB 最寄り駅の吉祥寺からすぐ近くというわけでもなく、ちょっと変わったところにあるなというのが正直な印象でしたが、連日予約で埋まっているそうで何よりです。ここを選んだ理由は何ですか。
森 ライヴハウスはこれまでに、埼玉の「ヒソミネ」、そしてバラカンさんにも以前お越しいただいた神楽坂の「神楽音」(かぐらね)を造ってきました。共同経営だった神楽音のほうは、現在は経営から離れていて、また新しいお店を模索していたんです。神楽音は駅から近い店でしたが、同じようなものにするより、もっと特徴的なライヴハウスを造りたいなと考えました。立地については、吉祥寺は昔から好きな街だったのですが、たまたま、元はアート・ギャラリーだったこの物件を見つけまして。確かに駅からは少し歩きますが、すぐ向かいに井の頭公園があるこの場所なら、いわゆるライヴハウスの煙たくてワルそうなイメージを一旦ゼロにすることもできるのではと。
PB ハハハハハ。
森 そんな新しいライヴハウスの在り方を提案したいなと思って造ったのがこのNEPOなんです。
PB 僕は実は45年くらい前に、ここから歩いて5分くらいのところに住んでいたんですよ。
森 そうなんですか(笑)。
PB 日本に来て初めて住んだところだから、よく覚えているんです。3年くらい暮らしていました。そのときにこういうお店があれば良かったのにね(笑)。でも、元がアート・ギャラリーだからか、確かに変わった造りですよね。
森 はい。実は1階のカフェは16時30分からは当店のフード&ドリンク・スペースとなります。つまり、夜のライヴは地下のライヴ・ホールと1階のカフェを2フロアで運営しています。
白水 1階のお店はシェアしているんですよ。
PB なるほど。それはいい考えですね。何年か前に、アムステルダムで友達のお兄さんが支配人をしている、ちょっと変わったジャズ・クラブに寄ってきました。ビルの中でしたが、レストラン・バーとその反対側にクラブのスペースがあり、会計は一緒にできるんです。日本にはなかなかそういうお店はありませんね。
森 そうですね。先ほどお話しした埼玉の「ヒソミネ」の近くで「bekkan」というダイニング・バーもやっていて、そこでもたまにライヴを開催しているんですが、ご飯を食べに来てくださるお客さんにとってはライヴでやっているのが好みの音楽とも限りません。また、どちらかというと友達とお話をしに来たお客さんにとっては音が邪魔になってしまうこともありますよね。そこで、ライヴとフードがこういうふうに分離してみるのがいいのではないかと考えたのです。こうすれば、ライヴを観に来たお客さん同士が食事とおしゃべりを楽しむこともできますからね。もちろん、1階で買ったフードを地下で食べていただくこともできますし、逆に、地下で買ったビールは1階で休みながら呑んでいただけます。
![1階には素敵なカフェが。[photo by Kana Tarumi] image v34_25](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/uploads/images/vol34/v34_25.jpg)
1階には素敵なカフェが。[photo by Kana Tarumi]
PB 1階のほうでは音は出さないのですか。
森 それも検討しているところで、1階のカフェでステージの映像を流したり、もしくはアコースティックなライヴやDJを1階でもやって、2フロアで別々の音楽をやってみるのも面白いかなと考えています。
PB それにしても、音にはこだわりがありそうですね。
森 そうなんですよ。神楽音のときもACOUSTIC REVIVEさんにご協力いただいて、ケーブルや電源を見直すことで「こんなにも音が変わるのか」と衝撃を受けまして(笑)。僕も白水もミュージシャンでもありますので、NEPOでも音の良さにはこだわっています。そして、100人以下というこのキャパは、これから出始めるバンドにとってもいちばん使う規模なんですね。ところが、これくらいの小さなお店だとPAが簡易的なものだったりして、ちゃんとした音が出せるのは数えるくらいしかないんです。でも僕らは、この広さで音にこだわったライヴハウスにしたいと思いました。
PB でも、このステージなら、けっこうな大所帯でもできそうですね。
白水 今夜も、10数人のバンドが出る予定です(笑)。意外と奥行きがありますので。
PB ステージに絨毯が敷いてあるのも珍しいですね。
森 これはヒソミネや神楽音と同じやり方なんですよ。海外のスタジオの絨毯の雰囲気が格好いいという単純な動機と(笑)、わりとリーズナブルに吸音できるというのもありますね。
PB そしてステージの壁にはリアルタイムな映像が映っているのも面白いですね。
森 この店はACOUSTIC REVIVEさんと同様にいろんな方にご協力をいただいていまして、このLEDディスプレイによる映像は知り合いの方に提供していただきました。プロジェクターも併用できるのですが、LEDディスプレイは照明効果もありますし、色も鮮やかですね。
白水 プロジェクターの2面照射とLEDを組み合わせています。背景となっているのはプロジェクターの映像で、発光が強いLEDの映像がそこに浮かび上がって見えています。
PB なるほど。
森 LEDディスプレイは大きなフェスでもよく使われますが、このキャパであえてやってみるのもいいかなと思って採り入れてみました。
白水 フェスの開放感や自由さをこのサイズのハコで再現してみようというのもありました。好きなアーティストを観たり、休んだり、お客さんが自分本位で選んで行動できるフェスの良さをいろんなところで意識しています。目の前が井の頭公園ということで、森の中でやっているフェスの小さいステージというか(笑)、そんな感じになるといいなと思っていました。

PB ところで、NEPOってどういう意味ですか。
森 “OPEN”を逆に読んだだけなのですが(笑)、やはり開放的な空間をという想いを込めています。また、ヒソミネ、神楽音と同じ“ね”の音を入れつつ、漢字で表記するなら“音歩”−−−音が歩くイメージも持たせています。
長内(ACOUSTIC REVIVE) このお店は会計システムも画期的なんですよ。
PB ほう。それはどんなものですか。
白水 スーパー銭湯などでよく活用されている(笑)、リストバンドを活用した決済システムです。いちいちお財布を出さずに何でも買えて、お会計は最後に現金やカードでお支払いいただけます。先ほどの開放的というキーワードにも結びつくもので、システム自体は外注せず、僕らで作りました。
森 ついでにこうすれば、ドリンクもフードもついつい多めに買ってくださるかと(笑)。
PB ハハハハハ。よく考えたねぇ。買い物にしろ何にしろ、お客さんが気持ちよく過ごせるように工夫するのは大事だと思います。
白水 僕は海外でのライヴ体験が多くて、アメリカやアジアなどいろんなところを観てきたんですが、例えばアメリカだと路上でお酒が呑めませんから、田舎ではそもそもライヴハウスくらいしか呑めるところがなかったりして、普段の生活の中に根付いていますよね。でも、日本でライヴを観る文化は、どちらかというと日常よりスペシャルな体験だと思うんですね。ワクワクして行くところというか。だからこそ、フェスには人がたくさん集まるわけですから、この店の駅からの遠さも、ギリギリなんとか受け入れていただけるのではないかと(笑)。
PB バスもありますしね。お店のすぐ前に停留所があるじゃないですか。
森 そうなんですよ。本数も山手線くらいあります(笑)。

日本のライヴハウス文化の良くないところをリセットしたい
PB それにしても、日本にはライヴハウスというスタイルのお店が多いですよね。もっと小さな規模のところも含め、各街に必ずと言っていいほどある。ここ吉祥寺も昔からライヴハウスが多かったですけど。
森 ライヴハウスで面白いのは、こちらがしっかりといいバンドをラインアップすれば、お客さんもちゃんと来てくれることです。飲食店は美味しい料理を作って今日はすごく混んでいたのに、次の日は天気が悪くて思ったほどいらっしゃらなかったり。読み切れないのは飲食店の宿命でもありますが、ライヴハウスは自分たちで日々作り上げるという感覚が強い場所だと思いますね。
PB 音響面で、ほかに何か工夫していることはありますか。
森 パワード・タイプのスピーカーとウーファーを入れているのですが、アコリバさんのケーブルとの相性もよく、メチャクチャいい音だと思っています。解像度が高くてエレクトリックな音楽にも合いますが、温かみも残しつつ自然な感じの音なので、バンド・サウンドにもマッチしています。
白水 このスピーカーは素直な音なので、アコリバさんの素直さがいじられることなく出ているような気がします。
長内 音を調整していく中で提供させていだいたのが、スピーカーの下に敷いている水晶が入ったアンダーボードです。大きなスピーカーなので特注になりましたが、敷いてみたら音はかなり変わりましたね。NEPOの皆さんが柔軟にいろんなことを工夫していく姿勢とACOUSTIC REVIVEのポリシーがすごく合っていると思いました。この音を聴いて、お客様がいつもニコニコしていらっしゃるのを見ると、お店が意図したものがいい形で出ていると感じます。本当に音楽が好きな人が集まっている感じで、そういうコミュニティが出来ているのは素晴らしいですね。
森 アコリバさんのケーブルは本当に高解像度で、音がすぐ近くで鮮明に聞こえる感じなのに、客席で隣の人とも会話できるんです。
白水 バンドがドーンとやっていて、すごく迫力を感じるんですけど、実際にはそれほど大きな音量ではないんです。音量を抑えていてもしっかり届くので、本当にしゃべれるんですよ。普通はバンドがガーッとやっていたら、隣の人の声は聞こえませんからね。そういう特徴は、音響のプロだけではなく、普通のお客さんにも感じていただいています。実は先日、楽器用のシールドをお客さんと聴き比べてみたのですが、もうみんなが一発で分かるくらいアコリバの製品は音が違いました。音に深みがあって、余計な成分が出ることもないのはすごいですね。
森 ライヴハウスでは、音の迫力というものを乱暴な方向に持っていきがちなところがあると思うんです。アコリバさんのケーブルが入ると、良くも悪くもごまかしが利きません。勢い任せというか、ライヴハウス文化の悪い意味での荒さというものをこのシステムでリセットできたらいいなと思っています。
PB 確かに、今日聴かせてもらったのはライヴハウスの音と言うより、分離も良くてスタジオのモニター・スピーカーのような感じがしました。そんなに音量を上げていないのに、とてもクリアに聞こえます。特に歌の存在感があったのも良かったですね。それにしても、『Gris-Gris』の「Gris-Gris Gumbo Ya Ya」のベイスはすごかったね(笑)。あんなに太い音で聴いたことがなかったのでちょっと驚きました。


メイン・スピーカーのELECTRO-VOICE ETX-35Pとサブ・ウーファーのETX-18SPはいずれもアンプを内蔵したパワード・モデル

サブ・ウーファーの下に敷いてあるのは天然水晶粒子が振動を抑制するACOUSTIC REVIVEのクオーツ・アンダーボード(特注品)

CDプレーヤーとして使用したPIONEER CDJ-800(左)とコンソールのALLEN&HEATH Qu-24

電源ケーブルをはじめ、NEPOのワイアリングは全面的にACOUSTIC REVIVE製品が使用されている

QRコード付きリストバンドを使用した会計システムにより、帰るときにまとめて精算できるのは便利

本日の試聴CD。左上はバラカンさんも試飲した当地縁の「深大寺ビール」

取材にご協力いただいた皆さんと。右はエンジニアの勝山敬亮さん






◎主な試聴システム
パワード・スピーカー:ELECTRO-VOICE ETX-35P、ETX-18SP(サブ・ウーファー)
コンソール:ALLEN&HEATH Qu-24
CDプレーヤー:PIONEER CDJ-800
ライヴハウス NEPO
2019年3月、東京・吉祥寺にオープンした「次世代型ライヴハウス=スマートヴェニュー」を掲げる新感覚の音楽空間は、音響・映像ともこだわりのシステムを導入し、さらに工夫を凝らしたフードやドリンクも好評。フェスのような開放感を目指す居心地の良いライヴハウスへようこそ!

東京都三鷹市下連雀1-17-4 GRATO井の頭公園 B1F
Tel.0422-26-9614
https://nepo.co.jp
アクセス:
電車◎JR中央本線 / 京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩約13分
JR中央本線「三鷹駅」より徒歩約14分
バス◎吉祥寺駅より 小田急バス 約5分「万助橋」下車 徒歩約0分
三鷹駅より 三鷹市コミュニティバス 明星学園ルート / 三鷹の森ジブリ美術館ルート 約5分「万助橋」下車 徒歩約0分



























































